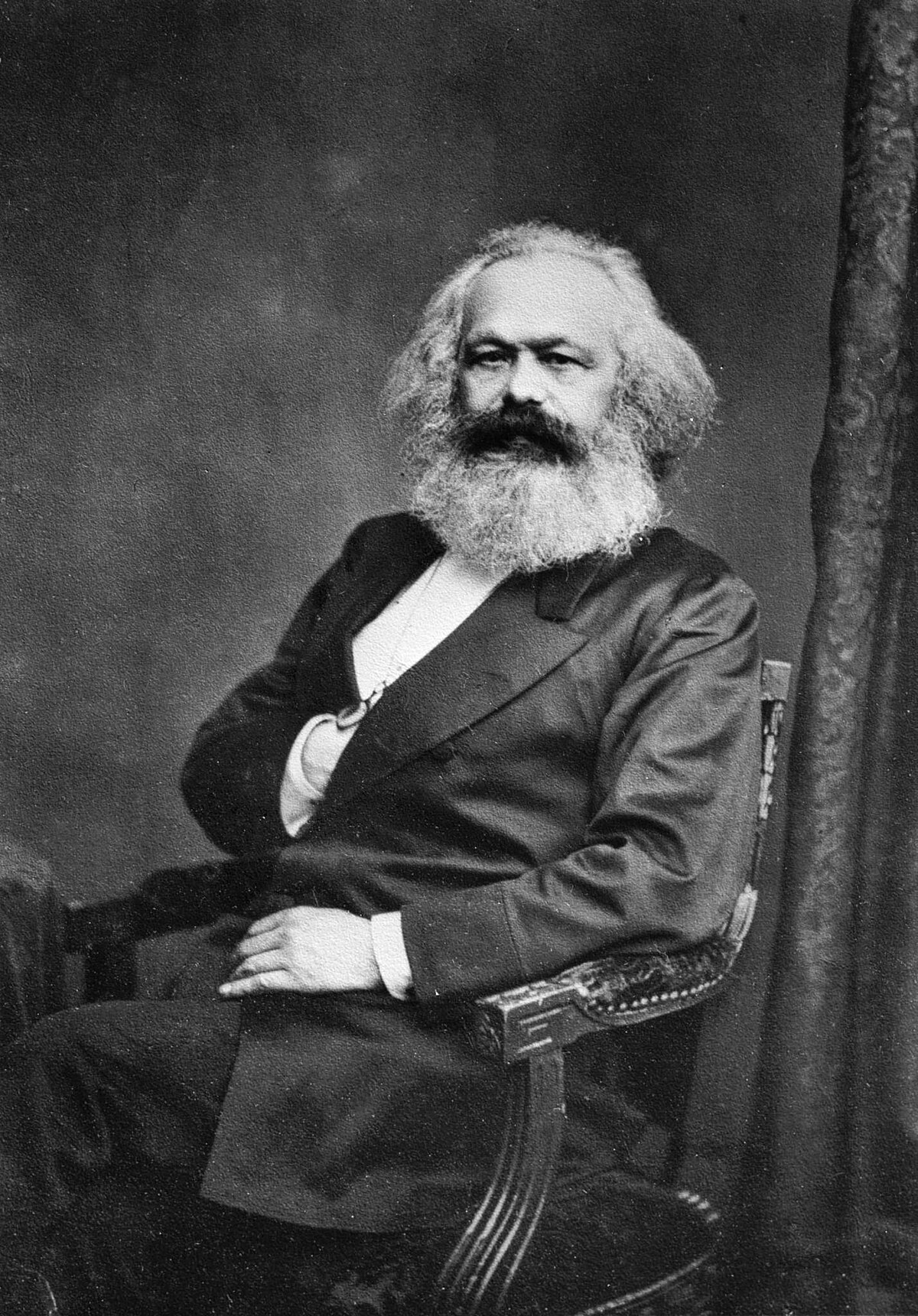ヘンリー・ジェイムズの「ねじの回転」(1898)は unreliable narrator の作品として有名である。実を言うと、この unreliable narrator という言葉には、わたしはちょっと違和感がある。なぜかというと語り手というのはもともと unreliable なものだからである。たとえば紫式部なんかは、「源氏物語」を書いて地獄に落ちると思われていた。「源氏物語」を読んでる人間だって地獄に落ちると思われたのである。フィクションというのは嘘のかたまりであって、そんなものを書いたり読んだりする人間はろくでもないということである。フィクションの語り手は嘘つきにほかならない。
ヘンリー・ジェイムズの「ねじの回転」(1898)は unreliable narrator の作品として有名である。実を言うと、この unreliable narrator という言葉には、わたしはちょっと違和感がある。なぜかというと語り手というのはもともと unreliable なものだからである。たとえば紫式部なんかは、「源氏物語」を書いて地獄に落ちると思われていた。「源氏物語」を読んでる人間だって地獄に落ちると思われたのである。フィクションというのは嘘のかたまりであって、そんなものを書いたり読んだりする人間はろくでもないということである。フィクションの語り手は嘘つきにほかならない。By Collier's Weekly, illustration by John La Farge - Beinecke Rare Book & Manuscript Library, Yale University, パブリック・ドメイン, Link
そこで初期の作家たちはいろいろと工夫を凝らし、自分たちの作品がでたらめや嘘ではないような見かけをほどこした。それが書簡体小説といわれるものだ。つまり作者は道を歩いているときに手紙の束を拾った。非常に面白い内容なのでここに発表しようと思う。ただし手紙の書き手は教養がなく綴りや文法の間違いがあるので、それは訂正しておく、云々、といったような前書きをつけたのである。自分が書いたものではない、他人が書いたものなのだ、そう主張することで物語の客観性を保証しようというのである。物語を作者自身から遠ざけるようなこの所作をディスタンスの技法などといったりする。
「ねじの回転」にはプロローグがついていて、これがやはりディスタンスの技法を使っている。「わたし」はあるとき知り合いたちと幽霊話をしあって楽しんだ。その知り合いの一人が、自分はとびきり怖い幽霊譚を知っている、という。その体験をした女性が書いた手記が彼の自宅の鍵の掛かった机の引き出しの中にある。それを彼は送らせて、知人たちに読み上げるという話である。つまり「ねじの回転」の本文は「わたし」が書いたものではないというわけだ。しかも手記はある男の家の「鍵の掛かった」机の引き出しの中にあった、という具合に、「わたし」と「手記」との距離を非常に強調している。
この距離はさっきも言ったように物語の客観性を保証するためのものであるはずなのだが……誰もが知っているように「ねじの回転」の本文、家庭教師の手記は、読めば読むほど、その記述の客観性が疑われるようなものなのである。小説の歴史を理論的に考える上で、「ねじの回転」が非常に重要なわけがここにある。
 |
| published by Valancourt Books |
タイトルを見るとわかるが、この本はステラ・マーベリー本人が書いたことになっている。ただし本文の前にはT・フィッシャー・アンウィンなる人物の序文(Preliminary Note)がついていて、「自分は以下の手記を手に入れた。奇怪で興味深い内容なので出版することにした」ということが書かれている。ディスタンスの技法を使っているのだ。もちろんこのアンウィンという人物は作者トマス・アンスティ・ガスリーのペルソナである。ガスリーは最初、自分の名を伏せて本を出版したのだが、すぐに彼が作者であることがばれてしまったらしい。
さて、この Preliminary Note のあとには手記の著者ステラ自身の序文(Introduction)がついているのだが、ここからもう手記の真実性が問題となってくるのだ。ステラは記憶が曖昧にならないうちに、自分がやらかした犯罪とも見える行為を、正確に、公平に書きつけようと思う、と言っている。なるほど確かに記憶が鮮明なうちに事実関係を書きつけておこうとすることはよくある。しかし続けて彼女は「たぶんわたしが真実を書いていると思う人はあまりないだろう。しかしそうであってもかまいはしない。もうすでにわたしは、外の世界の人がどう考えようと気にしなくなっているのだから」とも言っている。ここまで来ると読者はこの手記を素直に読むことはできないことをぼんやりと悟るだろう。彼女自身が「真実を書いていると思う人はあまりない」と言っているだけではない。「外の人」というところを読んで、この人は牢獄か精神病院(asylum)に入っているのだなと勘づくからである。犯罪人、あるいは精神異常が書いた手記となれば、誰もが眉に唾して読むことになる。しかもその犯罪人、あるいは精神異常すら「真実を書いているとは思う人はあまりないだろう」というくらいの内容ともなれば、なおさら身がまえて読むことになる。