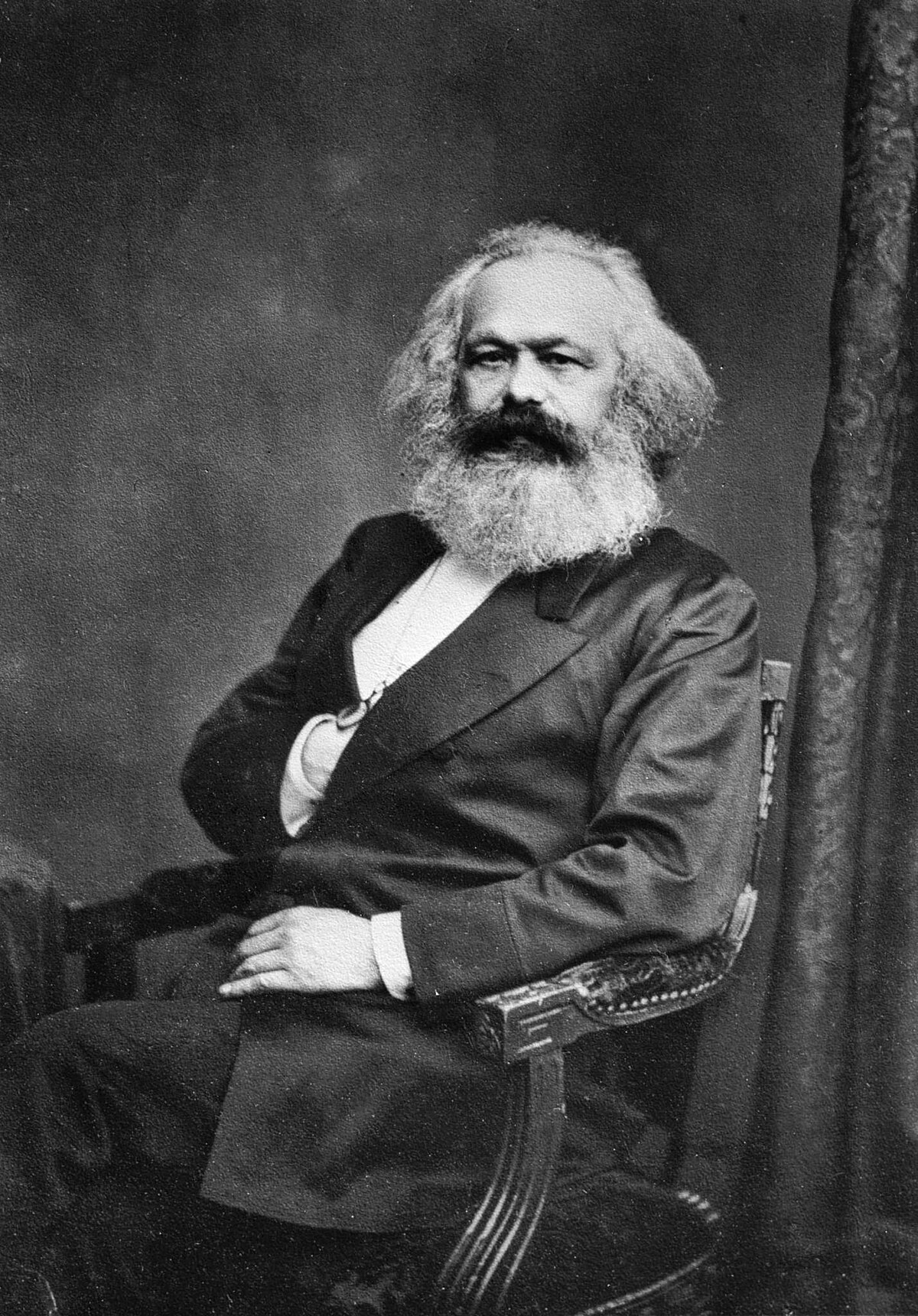五
最後に本作のテーマにかかわる問題点を指摘しておきましょう。現代の目から見ても非常に興味深い問題が読み取れます。
「悪魔の悲しみ」はファウスト伝説にのっとった物語です。ファウスト伝説というのは、現世的利益(金を儲ける、美人と結婚する、など)を得る代わりに悪魔に魂を売るという、誰もがよく知っている話です。クリストファー・マーローの「ファウスト博士」やゲーテの「ファウスト」、ミハイル・ブルガコフの「巨匠とマルガリータ」、ちょっと変わったところではウィリアム・ヒョーツバーグの「墜ちる天使」、いずれもファウスト伝説を利用した、あるいはファウスト伝説にひねりを加えた傑作です。マリー・コレーリもなかなか独創的な伝説を創り出しています。天使ルシファーは、神が人間に神性を付与するのを見て反対し、人間を徹底的に滅ぼしてやると叫ぶ。その結果ルシファーは天を追われ、人間を堕落させることに全力を尽くさなければならなくなる。これがパラドキシカルな状況のはじまりです。ルシファーは自分の目論見に成功したとき、つまり人間を堕落させたとき、みずから天への道を閉ざすことになり、失敗したとき、つまり人間が真の信仰心を見せたとき、天へと一歩近づくことができる。ルシオはこの伝説にたいして「詩的なところがある」といい、ジェフリー・テンペストも「美しい」などといっていますが、じつはここにこそ「悪魔の悲しみ」の最大の問題点が隠されているとわたしは思います。それを説明するには意外かもしれませんが、ジェフリーの信仰の構造、彼とシビルの夫婦関係を見なければなりません。
ジェフリーの信仰の構造は非常に奇怪です。金持ちになってからのジェフリーは道徳的に堕落していきます。ギャンブルをし、いかがわしい店で遊びほうける。彼は神を信じていません。しかも「男というものは好きなことをなんでも、好きなときに、好きなようにしてよいのだと考えていた。その気になれば獣より堕落することもできる」と考えている。ところが妻にたいしては「自分の汚れと正比例の完璧な純潔さを求める権利がある」と思っているのです。そして妻のシビルが自分と同じ堕落した人間であることが明白になると、彼は絶望し、湖のまわりをうろつきながら自殺を考える。なぜシビルが純潔で、信仰心を持つことが、彼にとってそれほどに大切なのでしょうか。彼自身が神に祈らないのなら、そして祈りなどまったく無意味だと思っているのなら、妻が祈らなくてもかまわないではありませんか。
一見すると矛盾撞着したジェフリーの態度からわかるのは、彼は神を否定しているが、しかし神を信じている他者を必要としているということです。あたかも彼は信仰心をみずからの外にはじき出して徹底した無神論者、堕落した存在になるけれども、外にはじき出した信仰心、貴重な自分の一部を、無用のものとして捨てることができず、それを他者に預け置いているかのようです。すなわち彼はみずから祈ることはないが、他者を通して祈るのです。ジェフリーはじつは神を信じている。ただしその信仰心は他者の中にあると言ってもいい。
神を信じる心、罪の意識といったものは、普通、神を信じる人の内部、罪を感じている人の内部にあると考えられています。しかしそうしたものが外部に存在することもありえるのです。この場合、その人と外部化された信仰心、罪の意識のあいだには、アンビバレントな関係が生じます。外部化された信仰心や罪の意識は、自分とはまるで正反対のものであり、自分にとっては無意味・無価値なものです。同時にそれは、もともと自分の一部であったもの、自分を構成する絶対的に必要な一部でもあるのです。こう考えれば、ジェフリーが無神論者であり、神を否定するけれども、同時に自分の信仰心を預け置いているシビルに信心深さや純潔さを要求する理由がわかります。彼女に信仰心がないということは、ジェフリーにとって何よりも大切な自分の一部がなくなることを意味するのですから。ジェフリーは彼女を「商品=もの」として扱いますが(シビルは女が「おもちゃ」扱いされることにたいして猛烈に抗議していますね)、彼女の信仰心のあるなしは彼の生死を左右しかねない重大事なのです。
これはとんでもなくおかしな「信」のありように思えるかもしれませんが、じつは谷崎潤一郎の「或る調書の一節」(一九二一)という短編なども、他者を通しての信というパラドクスを描いているのです。横道にそれるようで気が引けるのですが、面白いのでちょっとご紹介しましょう。
この短編はAとB、二人の会話という形で進行します。Aは警察の取調官、Bは犯罪者である土工の頭です。Bは結構な収入があるのですが、家の外に女をつくり、賭博、窃盗、強姦、殺人と悪事の限りを尽くしています。ジェフリーが悪徳にふけるのと同じですね。Bは「私は一生悪いことは止められません。私は善人になれたにしてもなりたいとは思わないのです。悪い事をする方がどうも面白いのです」と言います。
しかしBに罪の意識がまるでないかというと、そうではない。彼には女房がいて、彼が罪を犯すたびに、「どうか自首してください」「何卒改心してください」「真人間になってください」と言って、ぽろぽろと涙をこぼす。それを聞くとBはなんとなくしんみりしたいい気持ちになって自分も泣いてしまう。「胸の中がきれいに洗い清められるような気になる」。しかもこれがやめられない。この清浄な気持ちを味わうために、彼にとって女房は「非常に大切」な人間となる。とことん悪徳に浸っているのかと思いきや、実はBは「女房を通して」善良な心を持っているのです。
注意しなければいけないのは、かりにBが一時的に「胸の中がきれいに洗い清められるような気」になったとしても、それで彼が善人になるわけではない、ということです。彼は「後悔したって始まらないと思います」と言い放っている。彼はあくまで悪事を行うことに固執する。善良な心は彼にとって外部的なものなのです。しかし他方において彼は女房に泣いていさめられると「ただその時だけちょいと好い気持がする」、そしてそれが<span class="dotted">やめられない</span>。やめられないのは、「善良な心=外部的なもの」が実は内部的なものでもあるからです。この外部にして内部、自分と正反対のものであり、かつ自分そのものでもある他者に対して、Bはジェフリーと同じようにアンビバレントな態度を取ります。Bはジェフリーがシビルをもの扱いするように、妻を「犬猫同然」に扱う。しかし同時に彼女を「非常に必要な人間」とも見なしている。このパラドキシカルな関係に取調官は困惑し、しつこく土工を追求することになるのです。
イギリスでも日本でも外在化された「信」をテーマにした文学作品が書かれているという事実は非常に興味深い。しかも「悪魔の悲しみ」においてはヴィクトリア朝時代のブルジョア家族主義、「或る調書の一節」においては日本の家父長制家族が背景に存在しています。そしていずれの作品においても「夫」が、隷属する「妻」に祈る役目を押しつけている、あるいは押しつけようとしている。押しつけることによって夫は「効率的」に不道徳にふけることができたのではないでしょうか。西洋にはこんなジョークがあります。カトリックとプロテスタントは何をしてもいい。カトリックは罪を犯しても告解をすればいい。プロテスタントは罪を犯しながら罪の意識を感じればいい。これに悪のりしてつけ加えるなら、ヴィクトリア朝の紳士は何をしてもいい。家庭の天使である妻が、彼の代わりに祈っていれば。
これとコレーリが考えだしたルシファー伝説とは、どう関係しているのか。もうおわかりと思いますが、ルシファーも他者を通して祈っているのです。ルシファーは神に反抗し、神が造った人間を堕落させると誓った。彼は目的にむかってまっしぐらに突き進んでいく。つまり徹底して悪を行う、あるいは行わなければならない。しかし彼は明らかに神への信仰を持っています。ただしその信仰は他者によって表現されます。つまり人間がルシオ=悪魔を否定し、神を選び取るとき、彼の信仰心は満たされ、一歩天へ近づくことができる。コレーリは本作の最後で、彼が天国へ昇る壮麗な場面を描き出していますが、谷崎風に言えば「ちょいと好い気持ちがする」というわけです。
ジェフリーとシビルの関係、そしてルシオと人間の関係は完全にパラレルです。どちらの場合も前者は後者を見下しています。男は女より「すぐれた性」であり、ルシオにとって人間は「被造物」にすぎません。しかし前者は後者にその信仰心を預けていて、後者が神を信じることは前者にとって死活に関わる問題となる。前者は祈ることができません。しかし後者を通して祈るのです。ルシオはメイヴィスに、祈ることのできない者のために祈ってくれ、と言っていますね。このような転移された「信」の構造をファウスト伝説に組み込んだことこそ、コレーリの独創であったと思います。
「信」の外部化は「悪魔の悲しみ」を読み解く鍵になります。たとえば、ジェフリーの文学作品も、彼の「信」を外部化したものと考えることができます。彼がみずから書いたものであるにもかかわらず、今や富裕の身となった彼が信じていない神への信仰、理想的な生き方を描いているのですから。(ジェフリーの文学作品は彼がみずから製作した「商品」です。シビルもロンドンの結婚市場で彼が購入した「商品」です。この作品において人は科学や啓蒙のおかげで神の存在といった「迷妄」から解き放たれていますが、しかし彼らの代わりに「商品」が祈る役割を担わされている。「信」の外部化は資本主義の体制と関連していると思います。本書では悪魔も人間も自由意志を持ち、選択の自由を持っていることが強調されています。自由な個人は前資本主義体制においてはなかったもの、資本主義体制に至って存在するようになったものです。)またメイヴィスのユニークさは、彼女と信仰=作品の間に乖離がないことだということもわかります。さらにコレーリにとっては芸術が「信」の疎外の問題と切り離せないということも見えてくるでしょう。
すこしはしょった書き方をしてしまいましたが、もしも理論的なものに関心があり、「悪魔の悲しみ」をさらに深く読み解きたいとお考えになるのでしたら、ぜひ哲学者のスラヴォイ・ジジェクや、ロベルト・プファーラーを参照してください。とくにネット上でも読めるジジェクの The Interpassive Subject という短い論文、そしてプファーラーの On the Pleasure Principle in Culture という本は、「信」の転移の問題を明快に説明しているだけでなく、これがわれわれの日常のあらゆる局面(商品フェティシズムから子供の遊びに至るまで)に存在することを教えてくれます。「悪魔の悲しみ」は文学からこの問題を考えようとする人々にとって、格好の出発点になるのではないでしょうか。